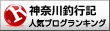肝硬変患者の骨髄細胞培養し点滴、山口大が新療法
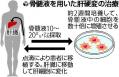
骨髄液の細胞が肝臓へ移動して正常な肝細胞に変化することで、症状の改善が期待できる。
3年以内の開始を目指す。
肝硬変はウイルス感染などで発症し、肝臓が本来の機能を失う。
国内の患者は40万~50万人に達する。
研究チームは2003年に肝硬変患者から約400ミリ・リットルの骨髄液を採取して点滴する臨床研究を開始。
これまで19人に実施し、15人の肝機能の改善や悪化抑制が確認された。
骨や脂肪などの細胞に変化できる骨髄液中の「間葉系幹細胞」が肝細胞に変化したり元々あった肝細胞を刺激したりして、正常な肝細胞が増えた結果とみられる。
ただし、約400ミリ・リットルの骨髄液を採取するためには、全身麻酔をかける必要がある。
全身麻酔に耐えられない、高齢や重篤な患者は、この治療法が受けられなかった。
研究チームが新たに臨床研究を目指す手法では、10~20ミリ・リットルの骨髄液を採取して約2週間培養し、点滴に必要な細胞数まで増やす。
全身麻酔が不要で重篤な患者らに向いているという。
(読売新聞)
■未経験可。勤務時間は自由出勤。時給1,500円~の副業。


iGoogleにガジェットを追加!
- 関連記事
-
-
 地球の「100兆倍」の水、120億光年のかなたに発見
2012/01/22
地球の「100兆倍」の水、120億光年のかなたに発見
2012/01/22
-
 難病も希望持って-静岡県立こども病院で乳児の心臓手術成功
2012/01/22
難病も希望持って-静岡県立こども病院で乳児の心臓手術成功
2012/01/22
-
 肝硬変患者の骨髄細胞培養し点滴、山口大が新療法
2012/01/19
肝硬変患者の骨髄細胞培養し点滴、山口大が新療法
2012/01/19
-
 平成の2つの大震災-仕組み・被害に相違点
2012/01/19
平成の2つの大震災-仕組み・被害に相違点
2012/01/19
-
 「紹介状なし」初診の負担増へ-大病院への集中緩和
2012/01/19
「紹介状なし」初診の負担増へ-大病院への集中緩和
2012/01/19
-