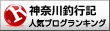3・11を経て・M9以上の地震、火山に「波及」-大噴火対策を本格検討
政府は東日本大震災の被害を重視し、広域に甚大な被害をもたらす火山の大規模な噴火の対策に乗り出す方針を決めた。
来年度、内閣府に有識者を交えた検討会を設置し、県境を越える避難や都市生活に影響する火山灰対策などを具体的に検討する。
日本は世界の活火山の1割が集中しているが、大規模噴火対策はこれまで手つかずだった。
震災は地震・津波対策だけでなく、火山の分野にも抜本的な見直しを迫ることになった。
11月17日、東京・霞が関の中央合同庁舎5号館5階の会議室に省庁の担当者や火山学者ら約30人が集まった。
富士山の大規模噴火がテーマの非公開の勉強会。
講師役の小山真人・静岡大教授が「想定外とされてきたことに今後は真面目に取り組むべきだ」と強調したうえで、04年に国主導で作製したハザードマップ(災害危険予測図)の見直しを訴え、出席者は皆うなずいた。
マップは1707年の宝永噴火を基に火砕流が山頂から約10キロまで到達すると予測。
小山氏はこれを大きく上回るシナリオとして、火山で起こる大きな山崩れ、「山体崩壊」の可能性を挙げた。
南東約15キロの静岡県御殿場市中心部は、約2900年前の山体崩壊で10メートル近く積もった土砂上にある。
小山氏は「周辺70万人の全面退避まで想定した避難計画が必要だ」と主張した。
20世紀以降、マグニチュード9以上を記録した地震は東日本大震災で6回目。

過去5回はいずれも翌日~3年後に近くの火山が噴火している。
今回の震災との類似性がいわれる貞観(じょうがん)地震(869年)が起きた9世紀には、富士山や伊豆大島、鳥海山などの噴火が相次いだ。
震災を機に火山に対する危機感が強まったのは必然だった。
火山学で言う大規模噴火とは火山灰や火砕流など総噴出物が10億立方メートル(東京ドーム806個分)を超すもので、国内では1914年の桜島が最後。
江戸時代以降100年に5~6回の頻度で起きた3億立方メートル超の中規模噴火も29年の北海道駒ケ岳からない。
こうした状況の中、国の対策は富士山ハザードマップ作製後、火山ごとで地元に対応を促すにとどまっている。
昨年度末の統計で、全国110の活火山のうち具体的な避難計画があるのは桜島だけ。
国は各火山の周辺人口すら把握せず、火山灰対策のマニュアルはない。
火山学をリードしてきた荒牧重雄・東京大名誉教授は「あまりにお寒い。国レベルで一元化した対応が必要」と指摘する。
昨年10~11月、インドネシア・ジャワ島中部のムラピ山が噴火、386人が死亡した。
ピーク時は約40万人が避難。数年に1度噴火することから同国で最も手厚い観測態勢が敷かれていたが、被害は想定を超えた。
政府は同年末、気象庁火山課長ら3人を現地に派遣。
初の海外火山の視察だった。
併せて勉強会を始めた直後に震災が発生。
大規模噴火時の問題点の洗い出しを本格化させ、周辺に多くの人が住む火山を念頭に対策を検討することになった。
「平和な時代が続きすぎた。日本の火山は今後活発化する」。
多くの火山学者の共通した見方だ。
小山氏は言う。「『3・11』で災害に想定外があることを大きな犠牲を払って皆が理解した。確率が低くても規模や被害が非常に大きい現象には備えが必要だ」
私たちの暮らしには、さまざまなリスクが複雑に潜み、突如として大きな影響を与え、逃れることはできない。
東日本大震災で改めて気づかされた。
リスクとどう向き合っていくか。
そのことを考えるシリーズを、自然災害から始めたい。
(毎日jp)
■未経験可。勤務時間は自由出勤。時給1,500円~の副業。


iGoogleにガジェットを追加!
- 関連記事
-
-
 「おめでとう」通話・メールの注意と規制-ケータイ各社
2011/12/31
「おめでとう」通話・メールの注意と規制-ケータイ各社
2011/12/31
-
 暮らしどうなる?チェルノブイリの経験から-内部被ばく減らす食事を…
2011/12/30
暮らしどうなる?チェルノブイリの経験から-内部被ばく減らす食事を…
2011/12/30
-
 3・11を経て・M9以上の地震、火山に「波及」-大噴火対策を本格検討
2011/12/30
3・11を経て・M9以上の地震、火山に「波及」-大噴火対策を本格検討
2011/12/30
-
 大震災・トモダチ作戦-米のアジア太平洋戦略、鮮明
2011/12/30
大震災・トモダチ作戦-米のアジア太平洋戦略、鮮明
2011/12/30
-
 M9-南海トラフ巨大地震「東日本より甚大」 震源域2倍に拡大
2011/12/28
M9-南海トラフ巨大地震「東日本より甚大」 震源域2倍に拡大
2011/12/28
-